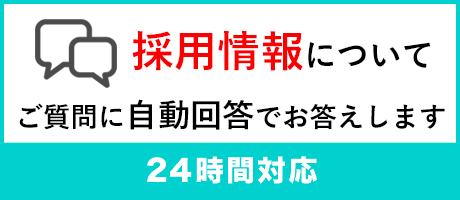イネカメムシ100超えるほ場で一斉調査 主に出穂後で発生確認

JAたじまでは、稲穂を加害する斑点米カメムシ類の一種「イネカメムシ」への警戒を強めています。7月9日と16日にそれぞれ、但馬全域の100を超えるほ場で一斉調査を実施。出穂が進むにつれて発生箇所が増えている結果となりました。JAでは生産者らに、ほ場を観察し、防除の準備をすすめているほか、イネカメムシの発生がある圃場については、2回防除を呼び掛けています。
JA管内では、昨年度からイネカメムシが全域で発生し、不稔米や斑点米などの被害をもたらしました。今年度も昨年度同様、関係機関らが協力して、発生状況の調査や分析などを行っています。
今回行った2回の調査ではそれぞれ、農業改良普及センターや県農業共済組合、市町職員、JA職員など約60人が、14班に分かれ、1ほ場につき2カ所、網を使用して10回すくいどりを行いました。
調査員が斑点米カメムシ種などを捕獲した場合は、スマホで撮影。画像をJA全農の営農管理システム「Z-GIS」と連携している日本農薬のアプリ「レイミーのAI病害虫雑草診断」にアップロードし、発生地域や密度などの情報を共有しました。7月9日(調査地点109ほ場)は10ほ場、7月16日(調査地点121ほ場)は30ほ場でイネカメムシの発生を確認しました。
調査はすでに6月下旬と7月上旬の2回行っており、16日の調査で計4回目。7月下旬にかけて同JA管内の主力品種「コシヒカリ」の出穂時期であることから、イネカメムシの発生は増加傾向が続きそうです。JAでは今後も、各関係機関と連携を取りながら、発生状況を確認し、情報発信に努めます。